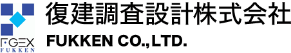IT・ビッグデータ
| 年度 | 業務名 | 発注者 | 表彰 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 令和4年度福山管内道路整備効果検討業務 | 国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所 | |
| 令和4年度山口南部地域道路概略検討外業務 | 国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所 | ||
| 令和4年度松江国道事務所管内道路マネジメント業務 | 国土交通省中国地方整備局松江国道事務所 | ||
| 早期実装にむけた先進的技術やデータを活用したスマートシティの実証調査(その7) | 国土交通省都市局(※松山スマートシティコンソーシアムによる受注) | ||
| 早期の社会実装を見据えたスマートシティの実証調査(その19) | 国土交通省都市局(※松山スマートシティコンソーシアムによる受注) | ||
| 2021 | 令和3年度マルチスケールな拠点空間計画のための新たな行動モデル研究 | 東京大学 | |
| 都市計画区域マスタープランに基づく備後圏都市構造の検討業務 | 広島県 | ||
| 2020 | 実装にむけた先進的技術やデータを活用したスマートシティの実証調査(その13) | 国土交通省都市局(※松山スマートシティコンソーシアムによる受注) | |
| 交通系ICカードデータ分析業務委託 | 長崎県長崎市 | ||
| 介入型プローブパーソン調査の実施に関する研究支援 | 広島大学 | ||
| マルチスケールな拠点空間計画のための新たな行動モデル研究 | 東京大学 | ||
| 都市形成のダイナミック分析に資する長期時系列土地情報のデジタル化 | 東京大学 | ||
| 市街地部の都市形成過程の解明に向けた土地変遷基礎調査に関する資料収集 | 東京大学 | ||
| 宮島口駐車場情報システム年間保守業務 | 広島県廿日市市 | ||
| 令和2年度 四国管内道路交通分析等業務 | 国土交通省四国地方整備局道路部 | ||
| 2019 | 先進的技術やデータを活用したスマートシティの実現手法検討調査(その9) | 国土交通省 | |
| スマートシティモデル事業の海外展開に関する検討・調査業務(その4) | 国土交通省 | ||
| 松山市大手町駅周辺 人流計測作業 | 東京大学 | ||
| 東京臨海部地区におけるプローブパーソン調査実施支援業務 | 東京大学 | ||
| 豊洲地区プローブパーソン調査結果取りまとめ支援業務 | 東京大学 | ||
| 松江国道管内道路マネジメント業務 | 国土交通省中国地方整備局 松江国道事務所 |
||
| 中国管内における幹線道路の役割・機能に関する検討業務 | 国土交通省中国地方整備局道路部 | ||
| 宮島口地区駐車場情報提供システム年間保守業務 | 広島県廿日市市 | ||
| 敬老パス利用状況等調査分析業務委託 | 鹿児島県鹿児島市 | ||
| R1輸送ルート検討に伴う交通量データ解析業務委託 | 大分県大分市 | ||
| 松山駅周辺行動実態調査業務委託 | 愛媛県松山市 | ||
| 介入型プローブパーソン調査の実施に関する研究支援業務 | 広島大学 | ||
| 2018 | 介入型プローブパーソン調査の実施に関する研究支援業務 | 広島大学 | |
| 宮島口地区駐車場情報提供システム年間保守業務 | 広島県廿日市市 | ||
| 三宮周辺地区における歩行者回遊性に関する評価・検証業務 | 神戸市都市局 | ||
| 2017 | 宮島口地区駐車場情報提供システム改良業務 | 広島県廿日市市 | |
| 宮島口地区駐車場情報提供システム年間保守業務 | 広島県廿日市市 | ||
| 広島国道事務所管内渋滞対策検討業務 | 国土交通省中国地方整備局 広島国道事務所 |
||
| 漁港のBCP策定およびリスク評価検討業務 | 民間企業 | ||
| 2016 | 福山河川国道管内道路整備効果検討業務 | 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所 |
|
| 中国管内における幹線道路の役割・機能検討 | 国土交通省中国地方整備局道路部 | ||
| 四国管内道路交通分析等業務 | 国土交通省四国地方整備局道路部 | ||
| 名阪国道周辺道路網調査業務 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 |
||
| 鳥取東部地域道路計画検討業務 | 国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 |
||
| 宮島口地区駐車場情報提供システム年間保守 | 広島県廿日市市 | ||
| 2015 | 松江国道管内道路マネジメント業務 | 国土交通省中国地方整備局 松江国道事務所 |
|
| 鳥取管内道路マネジメント資料作成業務 | 国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 |
||
| 平成27年度 四国管内道路交通調査等分析業務 | 国土交通省四国地方整備局道路部 | ||
| 中国管内幹線道路の役割・機能に関する検討 | 国土交通省中国地方整備局道路部 | ||
| 宮島口地区駐車場情報提供システム年間保守 | 広島県廿日市市 | ||
| 拠点的漁港の水産物流通に係る防災・減災対策の検討調査 | 民間企業 | ||
| 復旧・復興期の交通サービスアプリケーションの実装 | 東京大学 | ||
| 2014 | 中国管内広域幹線道路整備計画検討業務 | 国土交通省中国地方整備局道路部 | |
| 漁港漁場施設の性能規定化等技術検討 | 水産庁 | ||
| 広島都市圏バス活性化基本計画策定に係る検討等業務 | 広島市陸上交通地域協議会 | ||
| 宮島口地区駐車場情報提供システム年間保守 | 広島県廿日市市 | ||
| 2013 | 鳥取東部地域道路整備検討業務 | 国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 |
|
| 平成25年度 愛媛県内渋滞対策検討外業務 | 国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所 |
||
| 平成25年度 松山管内交通流動調査業務 | 国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所 |
||
| 福山管内道路整備効果検討業務 | 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所 |
||
| 中国地方における幹線道路の機能と役割に関する検討業務 | 国土交通省中国地方整備局道路部 | ||
| 広島都市圏における道路整備の必要性検討業務 | 国土交通省中国地方整備局 広島国道事務所 |
||
| スマートフォンを使った都心回遊PP調査 | 東京大学 | ||
| 平成25年度鹿児島国道管内交通検討業務 | 国土交通省九州地方整備局 鹿児島国道事務所 |
||
| 2012 | プローブパーソンデータの基礎解析作業 | 東京大学 | |
| 平成24年度 道改単債高委第2号設計委託 | 大分県豊後高田土木事務所 | ||
| 平成24年度松山管内プローブデータ収集・分析業務 | 国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所 |
||
| 平成24年度 愛媛県内渋滞対策検討業務 | 国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所 |
||
| 平成24年度鹿児島都市圏道路交通検討業務 | 国土交通省九州地方整備局 鹿児島国道事務所 |
||
| 2011 | 家庭内電力消費量を考慮したプローブパーソン調査 | 東京大学 | |
| ICTを活用した観光地における移動支援に関する調査業務 | 国土交通省総合政策局 | ||
| 平成23年度 愛媛県内渋滞対策検討業務 | 国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所 |
||
| 2010 | 福山管内道路整備効果検討業務 | 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所 |
|
| 松江国道管内交通流動調査業務 | 国土交通省中国地方整備局 松江国道事務所 |
||
| 広島・呉・岩国地域における外国人観光客の移動容易化のための 言語バリアフリー化調査 |
国土交通省中国運輸局企画観光部 | ||
| バス接近表示システム構築検討業務委託 | 広島県福山市 | ||
| 音声出力型ITS車載器を用いたITSスポットサービスの有効性検証に関する業務 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | ||
| 2009 | 平成21年度プローブデータ収集・分析業務委託 | 国土交通省四国地方整備局 香川河川国道事務所 |
|
| 道路行政マネジメント検討業務 | 国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 |
||
| 道路整備効果等検討業務 | 国土交通省中国地方整備局道路部 | ||
| 2008 | 松山市域EST普及推進地域モデル事業等委託業務 | NPOまちづくり支援えひめ | |
| 松山市交通戦略策定調査業務委託 | 愛媛県松山市 | ||
| 2007 | 福山都市圏交通結節点事業検討業務 | 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所 |
|
| 平成19年度松山都市圏交通環境まちづくりITS検討業務委託 | 国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所 |
||
| 2006 | 平成18年度松山都市圏における総合交通円滑化調査業務委託 | 国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所 |
|
| プローブデータ活用方策検討業務 | 国土交通省中国地方整備局 中国幹線国道調査事務所 |
||
| 平成18年度 松山都市圏交通環境まちづくりITS検討業務委託 | 国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所 |